あなたの夫、こんな言動はありませんか?
- 何をしても認めてくれない
- こちらの気持ちを全て否定される
- いつも自分だけが正しい態度
- 外ではいい顔、家では冷たい
「辛い」と思っても、
「私が弱いだけ」「普通の夫婦でもあること」
そう自分を責めてしまう。
でも、その違和感は
モラハラのサインかもしれません。
私も8年間、ずっと疑い続けてきました。
「これって普通?」
「大げさに考えすぎ?」
この記事では、
私が体験してきた “気づきにくいモラハラの特徴12項目” をまとめます。
同じようにもがいている誰かのために。
モラハラかもしれない夫の特徴 12選
1|「ありがとう」「ごめんね」が言えない
私が何をしても「当然」。
私が傷ついても「お前が悪い」。
「言ってほしい」と伝えると
「思ってもいないことは言えない」
感謝も謝罪も拒否される関係でした。
関連記事
2|やめてほしいと言ってもやめない
「その言い方がつらい」と伝えても
- 「それがおかしい」
- 「今さら直せない」
お願いはいつも踏みにじられる。
私の気持ちは常に後回しでした。
関連記事
3|義父もモラハラ気質
夫の言動の背景には、
義父の強い支配気質がありました。
「育った環境の影響」
そう思いつつも、
傷つける言動は正当化できません。
関連記事
4|自分だけが絶対に正しい
反論をすると、
「お前は理解できない」
「論理的じゃない」
話し合いではなく
正しさの押し付けになっていきました。
関連記事
5|自分には甘く、他人には厳しい
私には厳しく
「間違っている」と断言するくせに、
同じことを自分がすると平気。
矛盾の中で、私だけ責められる関係。
関連記事
6|相手の気持ちを理屈で封じる
「悲しかった」と言っても
- 「それは事実じゃない」
- 「主観だろ」
感情を否定し、揚げ足を取る。
ガスライティングそのものでした。
関連記事
7|相談しても、自分の得だけ考える
「どう思う?」と聞いても、
返ってくるのは
彼が得する提案
“家族として一緒に考える”
という姿勢はありませんでした。
8|外では仕事ができる
外での評価は高く、周囲には好印象。
だから余計に、
家庭内での苦しみを理解してもらえない。
孤独なモラハラでした。
9|結局、全部私のせいになる
どんな結果でも最後は
「説明が悪い」
「気が利かない」
「お前が悪い」
責任を押し付けられるたび
心が削られていく。
関連記事
10|人を褒めることができない
どんなに努力しても、
「当たり前」
存在価値を否定する関わり方でした。
11|家族を「自分の所有物」だと思っている
私の意見より、
夫の思い通りに動くことが当然。
尊重や思いやりはなく、
支配と服従がベースになっていました。
12|自責の概念がない
- 傷つけても気にしない
- 悪いのは常に相手
- 自分は正しいと信じて疑わない
だからこそ、
改善がとても難しい相手でした。
終わりに——「これは心を壊す関わり方」
正直、
「モラハラ」と言葉にするのは怖かった。
夫を悪者にしたいわけじゃない。
でも、
長い間、確かに心を壊され続けてきた
その現実には
ちゃんと名前をつけてあげたかったのです。
結婚して8年。
今も私は、夫のモラハラに向き合っています。
もし今、同じように苦しんでいる人がいるなら
一人で戦わなくていい
- 逃げるという選択肢は正しい
- 誰かを頼ることは弱さじゃない
モラハラ加害者は自責性が低く、変わりにくいから。
あなたの感じている痛みは、
決して間違いじゃない。
どうか自分を大切にして
生き延びてください。
この言葉が、
あなたの心の支えになりますように。
この記事もおすすめ
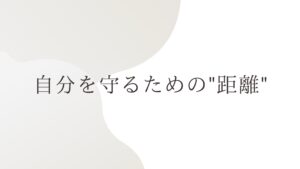
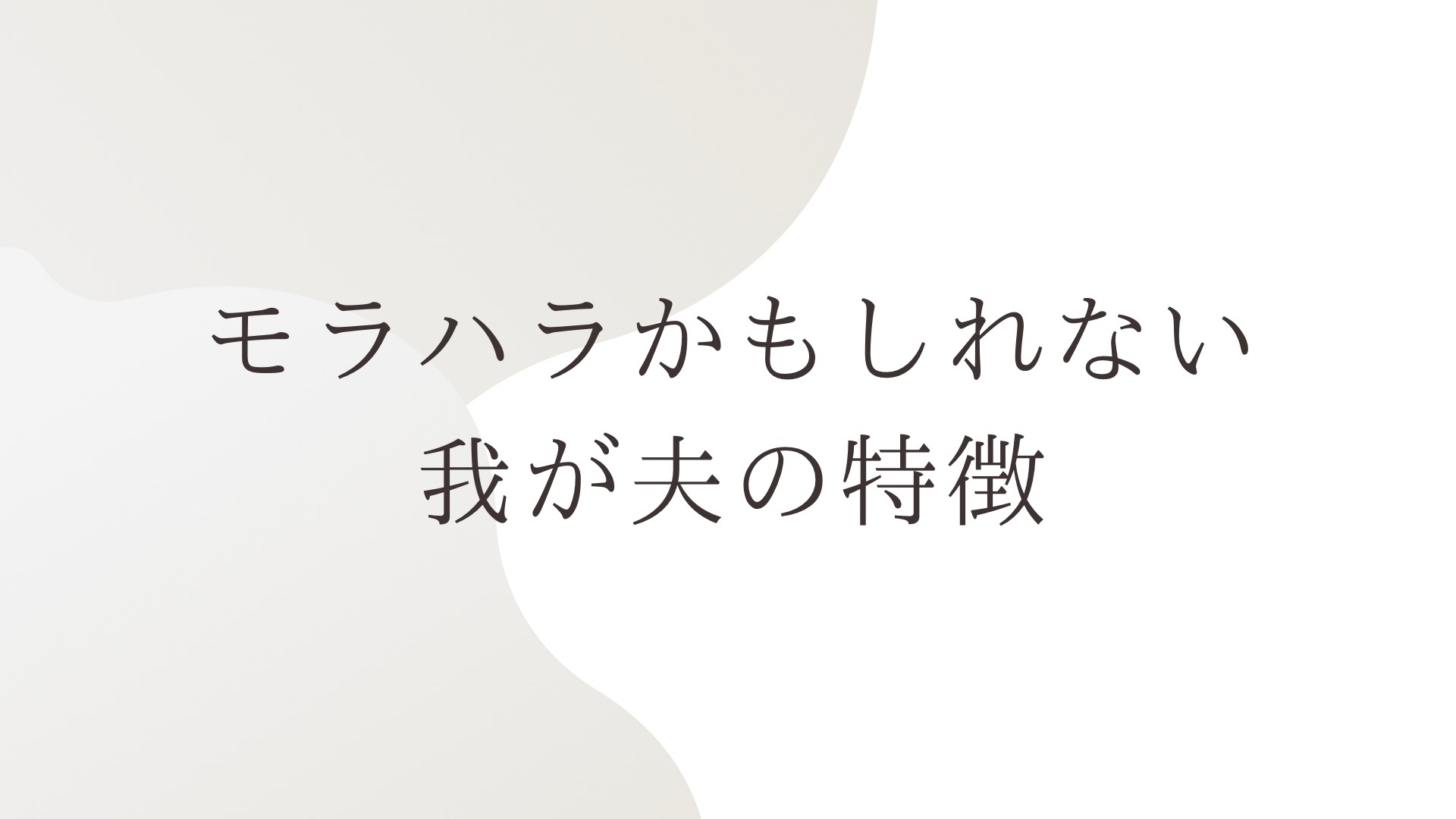
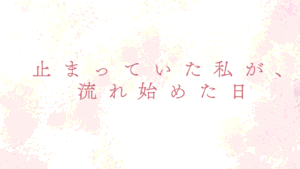
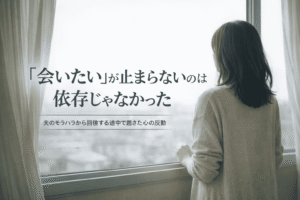
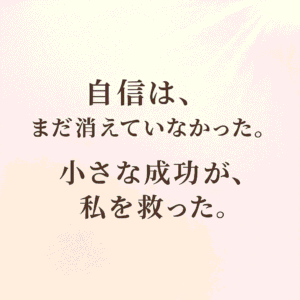
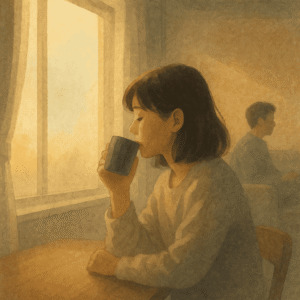
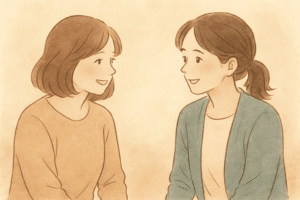
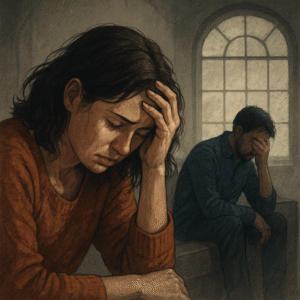
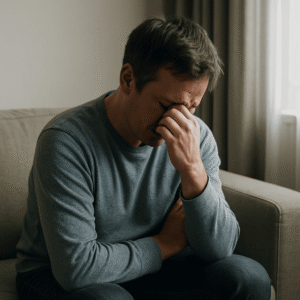
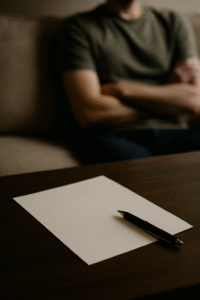
コメント